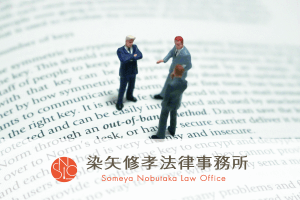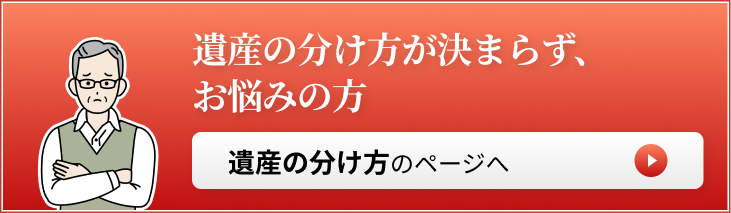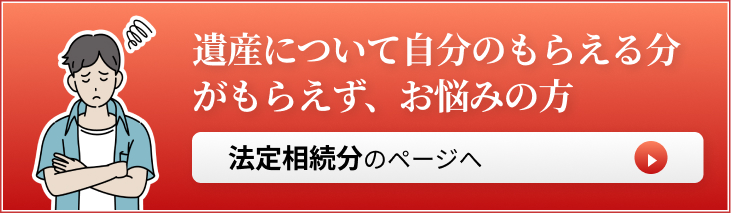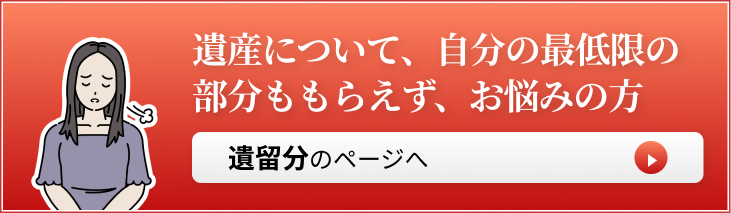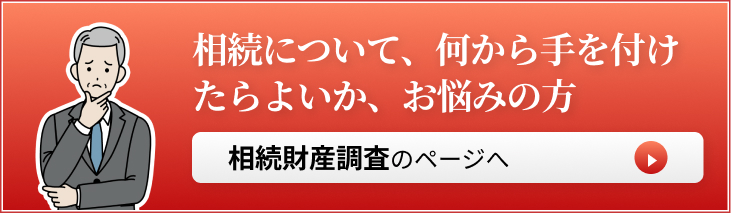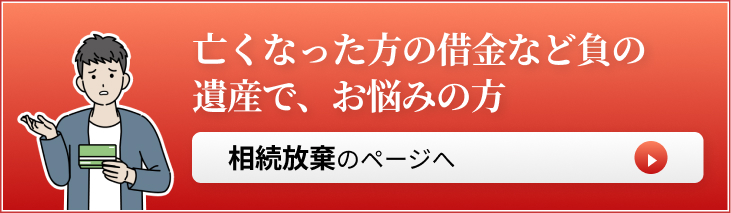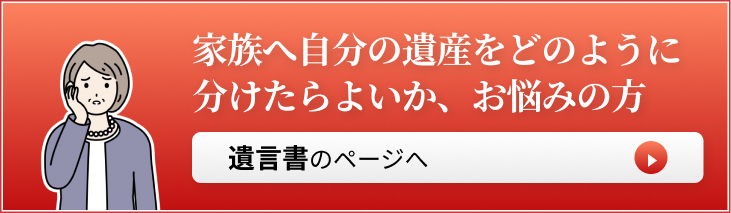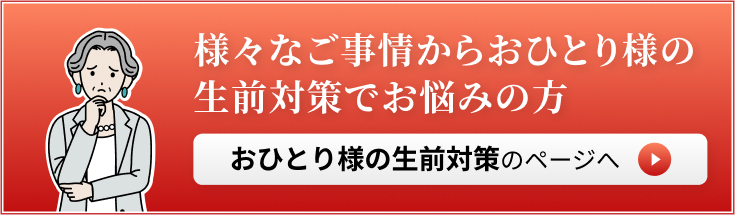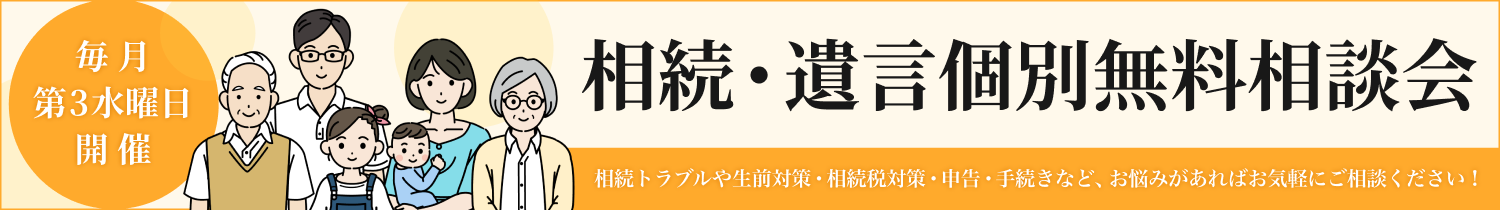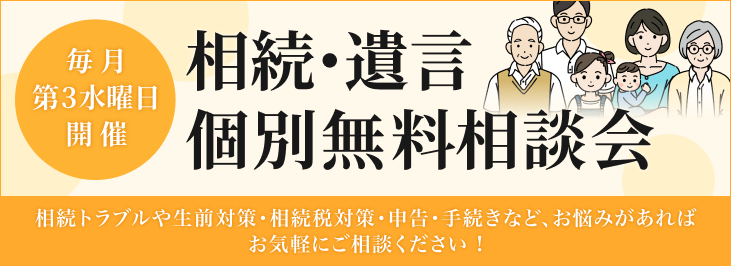財産を持っている方が無くなったとき、相続の問題が起きますよね。
このとき、法定相続人(民法で定められた財産を受け継ぐ権利を持つ人)それぞれに法定相続分(受け継ぐことができる割合)が定められています。
しかし、法定相続分よりも遺言書のほうが優先されるため、実際には法定相続分よりも少ない財産しか相続できないケースもあります。
そこで登場するのが「遺留分権者と遺留分減殺請求」です。一体、どのような制度なのでしょうか。
1 遺留分とは?遺言書の内容に対抗できるの?
冒頭でも述べたように、法定相続人が法定相続分に従って相続を受けようとしたとしても、遺言書の内容によって取り分が減ってしまうことがあります。
基本的には遺言書の内容が優先されますが、法定相続分と比較してあまりにも減少幅が大きい場合は、相続人の期待を裏切るとともにトラブルの種になってしまいますよね。
このような法定相続人の不利益を防止するため、民法では「遺留分」という考え方を設けています。
遺留分とは、簡単に言えば「遺言書でも変更できない最低限の取り分」のこと。
つまり遺留分は、法定相続人が相続する財産の最低ラインを保障しているわけですね。
日本の相続制度には「近親者の生活権を保障する」という考え方があり、いくら遺言書で取り分を変更したとしても、法定相続人は最低限の財産を相続できるよう配慮されています。
さらに、この遺留分を相続する権利を持つ者を「遺留分権利者」、遺留分を請求する手続きを「遺留分減殺請求」として定めています。
(遺留分の帰属及びその割合)
第1028条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一”
2 遺留分権利者になれる人はどんな人か?
この遺留分ですが、亡くなった方の近親者であれば、誰もが遺留分権利者になれるわけではありません。
前述した民法第1028条で述べている通り、遺留分権利者になれるのは「兄弟姉妹以外」の法定相続人です。
例えば3人兄弟の末っ子であるAさんが無くなったとき、その妻であるBさん、息子であるCさん、娘であるDさん及びAさんのご両親が遺留分権利者となります。
一方、Aさんの兄であるEさんやFさんには、遺留分権は認められません。
また、CさんやDさんにお子さんがおり、すでにCさんやDさんが死亡している場合、そのお子さんも遺留分権利者となります。
専門用語でいうと「法定相続人の代襲相続人」ですね。したがって、遺留分権利者をまとめると以下のようになります。
1.兄弟姉妹を除く法定相続人(子・直系尊属(祖父母や養父母など)・配偶者)
2.兄弟姉妹を除く法定相続人の代襲相続人(本件の場合はAさんの孫にあたる者)
3.上記遺留分権利者からの承継人
3 遺留分減殺請求の手続きとは?
遺留分権利者にあたる者は、遺言書に書かれている相続の内容が自分の遺留分よりも少なかった場合、その差分を請求できます。
これが「遺留分減殺請求」で、計算や手続きがやや煩雑です。
まず法定相続分を計算し、それに前述した第1028条の割合をかけ、実際の取り分と比較して遺留分減殺請求にかける財産を計算します。
その後実際に請求を行うわけですが、これには形式的な決まりがなく、裁判外で請求しても、裁判所に訴訟を提起しても良いわけです。
要は話し合いか訴訟かということですね。どちらにしても相応のコストがかかります。
話し合いがうまくまとまれば良いのですが、一度受け取った財産を素直に返還する方ばかりとは限りません。
また、裁判所で手続きする場合でも「遺留分減殺による物件返還請求調停」や訴訟を行わなければならず、法律の素人にはやや荷が重い手続きとなります。
さらに遺留分減殺請求権の消滅時効はたった1年であり、できるだけ早急に事を進める必要があります。
もし話し合いで決着がつきそうになければ、迅速かつ公平な手続きを行うプロ(弁護士)の手を借りるべきです。
遺言書の内容に疑問を感じている方は、本来自分が相続できる最低限の財産を守るため、一刻も早く専門家に相談することをおすすめします。
 もし現在、相続問題に関してお悩みを持たれている場合には、弊所にお悩みをお聞かせください。
もし現在、相続問題に関してお悩みを持たれている場合には、弊所にお悩みをお聞かせください。
相続費用も気にする必要はございません。
初回1時間程度、相談料無料としております。
どうぞお気軽にご相談ください。
「いったい,何から手を付けたらよいか分からない。」
という,全く先の見えない状況でも大丈夫です。
弁護士はじめ弊所スタッフ一同,あなたの相続問題を「全力でサポート」いたします。

-300x200.jpg)